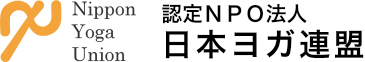お元気ですか?ココロとカラダ
新テキストに関する質問
2025.9.4追加
Q:皆さん瞑想よりも眠りの方に近くなってしまいます(2日目 瞑想)
A:
初心者のサマタ瞑想には細やかな誘導が必要かと思います。
ろうそく瞑想であればその明るさ、広がり、動きの様子などを、開眼・閉眼を交互に繰り返し持続集中して見続けなければなりません。
それができるように細かに呼吸の誘導をしていくと睡魔から遠ざかることができます。
また集中点もわかりやすくなりますね。
対象物と一体化することで集中力が増しますからその分雑念が無くなり、心が囚われなくなる=心を止することができる瞑想、それがサマタ瞑想です。
2025.3.28追加
Chapter10「アーユルヴェーダとヨガ」については、こちらも参考にしてください。
Q:P175の胆経の説明文で「左耳を腕につけて」とありますが、反対側を行うときに右耳は腕につけてと説明をしても良いでしょうか?
A:
動画でも「反対側も同様に行います」と言っていますので、右側も同じように行います。
(反対の動きは右腕を右耳につけて右へ倒す。このとき意識の移行は初回同様。)
耳を腕につけて倒す理由は、体側が縮み過ぎないよう上へ伸びやすくなるような状態を保つ為です。
肉体により歪み、縮み、たるみがない状態の方が氣は流れやすい、ということです。
Q:太陽礼拝(れいはい)を太陽礼拝(らいはい)と言う理由はなんですか?
A:
礼拝(らいはい)は仏教で用いられる「呉音」読みで、礼拝(れいはい)はキリスト教やイスラム教で用いられる「漢音」です。
呉音とは、中国は南方の時代に使われた読み方で、実は漢音より先に日本に伝来されたと言われていて、比較的古い歴史がある文献や仏教典には「らいはい」の読みが使用されています。
テキストで礼拝(らいはい)と読ませる理由ですが、それは沖ヨガがインドのヨガとそもそもアジアの密教・仏教、そして日本神道の哲学思想や生命技術を総合的にまとめた瑜伽(ヨガ)だからです。
因みに、テキストで紹介している坐法の安定座(あんじょうざ)、十段階にでてくる疑念(ぎょうねん)も仏教経典に在る呉音の読み方で、沖ヨガはこの読み方にて教えています。
2022.6.14追加
Q:p.66長座前屈の効果について
大腿四頭筋の柔軟とあるのですが、大腿四頭筋はハムストリングスの拮抗筋なので、大腿四頭筋を収縮させるとハムストリングスが弛緩しやすくなると学びました。特にかかとを突き出し、足先をスネの方にひきつけると収縮します。
大腿四頭筋が収縮ののち、柔軟性が生まれるという理解で良いのでしょうか?
A:
<柔軟性に対する概念>
・大腿四頭筋はハムストリングスの拮抗筋なので、大腿四頭筋を収縮させるとハムストリングスが弛緩しやすくなる
→仰る通り、アウターマッスルの拮抗系筋肉には陰陽の関係性があります。
・特にかかとを突き出し、足先をスネの方にひきつけると収縮します
→膝周りの筋肉(大腿四頭筋群)に力を入れながら行うことで統一体になります。
・大腿四頭筋が収縮ののち、柔軟性が生まれるという理解で良いのでしょうか?
→収縮したから柔軟性が生まれる、という筋肉論的なことではなく、ヨガ的にご説明をしてみて下さい。
例えば…修正柔軟法(a)では上体を前後に動かします。
この動きは、拮抗系の筋肉に緊張弛緩(陰陽)の交互刺激を与える反復法ですから、呼吸が筋肉に及ぼす影響力を使いながら、筋肉の状態をコントロールし、統一体に近づけていく動きになります。
そしてアーサナを保つ時には、下半身は心地よい緊張(陽の状態)を保ち、上半身は重力に任せるように力を抜きながら(陰の状態で)無理ない無駄ない姿勢に整える(タパス)に集中します。(写真➃)
アーサナは、肉体の陰陽バランスをプラティヤハーラしながらより良い状態に近づけていく集中力で深まります。
幾度も幾度も同じアーサナをすること(スヴァディアーヤ)で、「自身に丁度に良い状態=ヨガ」が出来上がっていきます。
自分の努力を神託(イシュワラプラニダーナ)します。
このプロセスが生命即神への気づきとなります。
このようにご説明下さると、ヨガアーサナが決して単なるストレッチではないこと、一人一ヨガに依る心身変容の過程だと言うことがわかります。
※鳩尾がつる人は上半身が力み過ぎです。
2022.5.10追加
Q:P6の下から7行目「知識に基づかない行動」「行動を伴わない知識」の両方は無意味とありますが、その前の文章のカルマとどのように繋げて説明すればよいですか?
A:
輪廻転生の思想においては、あらゆる行いには善き悪しきのカルマが存在するのだからそのカルマから解放されることを目的としたカルマヨガを行いなさいとしています。
沖ヨガでは解放される具体的な方法として、より高い次元の気づきを得る「信じるな・疑うな・確かめよ」、即ち実践哲学である「知行合一した生きかた」をしなさいと教えています。
知行合一とは、知識と行動が一致した体験を言います。
そうか、わかった!ということが己のカルマを修正する気づきとなりえるのであって、そうでなければ本当の気づきは得られないのだ、と教えているのです。
インドでいう「カルマ」とは因果応報の法則であり、魂レベルでのカルマからの解放が必要です。
ところがほとんどの人は自分の喜びの内にて解放されると思い込んでいて、魂の喜びに考えが至りません。
このことから沖ヨガでは最終二段階を、人知を超える魂が神の心(真理法則)と一致して喜び輝く、本来の境地へ導く段階として加えています。
過去世、未来世のことにとらわれることなく「Be here now」である今世の生き方に感謝をもって実践する求道心は、より高い次元の気づきを促す真のカルマヨガの教えなのです。
Q:P43下から4行目「キリスト教でいう十字架の真意と同じです」とありますが「十字架の真意」を検索すると贖罪、自己犠牲、愛のシンボルとでてきます。この段落ではどういう意味にとればいいですか?
十字架の真意とは何ですか?十字架の真意を前の文章につなげてどう説明をすればよいですか?
A:
まず、グーグル先生での検索ではここが意味する解答は決してでてこないでしょう。なぜならここでは沖先生の十字架に対する解釈で説明しているからです。
<キリスト教による十字架の真意とは>
キリスト教は一神教です。神と神の子である人との契約が戒律(聖書)となっています。
従って悪いことをするものは、大いなる神によってその罪をゆるされ、神の為にあらゆるものを奉げる生きかたをするのが善いとし、神こそが愛(アガぺ)のシンボルだとして、神主の御前で十字架に貼り付けになったキリストを偶像としました。
キリスト教はこの十字架を崇めるよう教えを説いて悩める人々の心を救済しているのです。
<沖ヨガによる十字架の真意とは>
外に神をみるのとは異なる生命即神の考え方や、多神教のヒンズー教、そして日本の神道の教え、仏教の数多に存在するご先祖様へ感謝する心、
山川草木悉皆仏性の教えなどの深い解釈を囚われない心への導きとし、十字架の解釈を「縦のつながりにたいする御恩と横のつながりにたいする御恩への感謝の心」としています。
縦は過去から未来、過去に頂いたあらゆるお陰様に感謝をし、今を懸命に生きることで未来を創造していきます。
横は今自分が頂いている眼に見えないものも含めあらゆるお陰様に感謝することの意味です。
それには、「狭い偏ったものの見方ではなく、幅広く深く感じ考え行い、あらゆることに尊いご縁を感じる事です。目にみえないご縁、おかげ、罪などを幅広く深い立場でみることが大切です。いわば水平思考と垂直思考を一つにして把握する、ということです。」
沖先生は、十字架にも同じ真意の教えがあると直感され、このように例えられたのだと思います。
すべて無念、無想、無私,無我、無条件という、人知的条件から解放された状態でなければ真の自由者にはなりえない。
それを求めて知行合一の生活することを冥想行法と言いますが、冥想行法あっての十字架の真意という事だと思います。
※ちなみに、中島みゆきさんの歌に「糸」というのがありますが、あれはもっともわかりやすい、子供でも理解しやすい現代流の十字架の真意の表現かもしれませんね。笑
2022.3.24追加
Q:旧テキストにあった食品の表を削除した理由はなんですか?
A:
そもそもマクロビオティック食品表は医師、石塚左玄先生の陰陽独自論から成るもので、その陰陽分類の仕方には中医学の陰陽論とは異なります。
石塚先生のお弟子さんである桜沢如一博士が自身の講演会の中で陰陽食滋養法として発表したことで世界中にこの思想が広まり中医学の食事論のように言われていますが、そもそも中医学の食事養生法は医食同源を土台とする「薬膳」に在ります。
新テキストでは中医学への誤解を招くような掲載の仕方は控え、食の偏りとなる提示を避けるよう、あえて削除させていただきました。
Q:経絡体操の動きが旧テキストと違っているのはなぜですか?
A:
旧テキストの動きは肉体的で、この章で理解してほしい「気のからだ」の動きとしては不十分です。
気功的動きには意識の移動(イメージ)は欠かせません。
経絡のラインに沿って手で導くように氣を誘導する形に適したものとして、新たにご紹介しております。
Q:テキストP73の②の動きの説明、「両手で床を押しながら」がよくわかりません。
A:
「手で押しながら・・・の順に持ち上げる」ところは講師がもう少し詳しくご説明下さい。
例えば「骨盤を床に押し付けて両手で押しあげるようなイメージで背骨を一つ一つ反らせていく」など、意識の移行を加えると分かりやすいと思います。
テキストのポーズ(写真)はあくまで基本です。コブラのアーサナスタイルは他にも様々あり、やりかたも様々です。
両手でしっかりと床を押し支え、その状態を完成させるコブラや浮きコブラのように両手を完全に床から浮かせてしまうものもあります。
いずれも一か所の力で保つのではなく、両腕、下半身、背中、腹部、頭部へと心地よく緊張していき、全身を協力させるよう意識を集中します。
より統一された状態を呼吸のコントロール力で深めていく、それがアーサナです。そのプロセスの詳しい部分は先生方の説明をお願いします。
Q:テキストP70のねじりは旧テキストとは違いますね。
A:
新旧どちらの形でも構わないのですが、新テキストでは下半身をより強固にし効果を得られやすい形を選びました。
アーサナは上虚下実の姿勢、陰陽エネルギーのバランスを調える効果があります。
この姿勢で足裏をきちんと大地(床)につけることは「捻り」の完成度に関わる土台として重要ですが、関節の柔軟性が関わるので最初は困難かもしれません。
その場合は下半身の姿勢を変えて行います。
例えば脚を伸ばして行うなど、筋肉や関節の負担を軽減しながら取り組むようにします。一人一ヨガ、工夫をしながら動かしましょう。
Q:コブラの禁忌はどう配慮すればよいですか?
A:
コブラのアーサナの禁忌事項は 反るという状態が健康状態に障る場合です。
腰の既往症(すべり症・ヘルニア・脊柱管狭窄・慢性ぎっくり)がある方や、現在腰痛が続いている方にこのアーサナは適しません。
また、健康体の人であっても修正法(抵抗法・関連部位法)で調えて肉体の症状が和らぐようにしてから行うと良いかもしれません。
…だからしません、…なのでできませんという状態を、どうしたらできるか?研究をして、できるよう指導しましょう。
Q:P74の修正柔軟法はどんな効果を狙っているのですか?
A:
骨盤と肋骨開閉の修正法になります。
魚のポーズは肋骨の開きとそれに関連する骨盤の状態を整えることが重要です。
骨盤のゆがみに前後・左右差があると肋骨の開閉にも困難を生じますから修正柔軟法をする必要があります。
Q:P78の写真ですが、拳の形や位置はどうなっていますか?
A:
バッタのこぶしの基本形は必ずしも決まってないでしょう。
統一体としては脇を締める効果がよりしっかりするような形が好ましいです。
テキストの両手の位置は下腹部の中心寄り、丹田を意識できる位置です。この位置が統一体に適しますが個人によって多少の違いがあるかと思います。
このアーサナを行い続けることで自分に適した形がわかってきますので、講師は生徒が自身で統一体を得られるよう誘導しましょう。
Q:P34、バストリカについてですが、最後の一吐きの出し方は同じリズム?それとも長く吐いて終わるのがよいでしょうか?
A:
その辺はこだわらなくてよいと思います。
この呼吸の効果は、エネルギーを高め機能を活発化することにありますからできるだけ力強く最後まで同じリズムで行えるよう訓練します。
回数や速度を変えながら違いを観察しましょう。最後は自然呼吸に戻します。
Q:太陽礼拝の最初の両手の挙げ方は前から?横から?
A:
テキストでは合掌の手を上げるとなっていますので当然前からになりますね。
挙げ方は様々あるようです。色々な方向から手を上げると肩や背中や関わるところを刺激しますし360度を意識し、胸(心)を四方八方へ広げる動きとすると心の扉であるアナハタを緩める効果が得られます。
手の挙げ方だけでなくポーズも様々取り入れて行ってみて下さい。
回数を重ねながら続けて行う事で、身体の修練、心の修養(四心一行)となります。
Q:三角のアーサナで、足巾を決めるときにわざわざ膝立ちになる理由がわかりません。
A:
片膝立ちは、立位の状態で体を支えるアライメントとして適切な足巾という意味があるそうです。
確かに行ってみて、写真の様な片膝立ちは合理的な方法だと感じます。
自分の足の長さくらいに、とか、1メートル弱とか、このぐらいで、という誘導は理解が様々になるようですが、片膝立ちの形ですとわかりやすく、決まります。
この時股関節・膝関節はきちんと90度にして、そのまま立ちます。立位の両足先の向きは大切ですので一人一人を先生がチェックしましょう。
正面を向いた姿勢で両手を左右一文字に伸ばし胸郭を均等に広げて丹田に意識を置くと、身長に対する上下率、骨盤・股関節回りに過不足のない適切な足の位置となります。
ただし、上半身の状態(メタボ、猫背)や、下肢の筋力、股関節筋群の柔軟性には個人差がありますので、動いてみた時に足巾を調整する必要がでてくると思います。
関節を傷めないようご指導願います。
Q:肩立ちのアーサナで、P89の⑤、床と垂直の所は水平の間違いでは?
A:
間違いではありません。下肢を骨盤上に正しく乗せるための表現として、旧テキストのものを引用しています。
が、写真がその一つ手前のプロセスのものであるため誤解を招いたのだと思います。
体の一部を空中へ持ち上げる場合、重力がかかる部分を傷めないようにインナーマッスルを上手に使う必要があります。
三角のアーサナでは上にあげた腕は重力にゆだねた状態で維持されています。
肩立ちのアーサナも同様に、まず鋤の形から両膝を額へ近づけ
⇒背中に当てた両手の形をきちんと整えて脇を締め背筋を支え、両脚の裏を天井方向へ向ける(上から5枚目の写真)
⇒⑤ひと息吸い、吐きながら膝を曲げたまま太腿が床と垂直になるよう持ち上げ背中をまっすぐにする。
※肩、上腕、肘で支える ←ここで骨盤の上に背骨(内臓)をのせて正姿勢の逆立ち状態へと整えていきます。重力に任せた無理のないところで保ちます。
旧テキストP63の写真、上から3枚目をご覧ください。このモデルは逆立ち正姿勢のインナーマッスルができあがっていますから太腿をある程度の垂直まで持ち上げることができています。
⑥の補足説明 ゆっくりと垂直になるように重心を骨盤上に移動させることで足を上に挙げた時に逆立ちがまっすぐになり逆立ちの正姿勢となります。
Q:東洋医学の実技で三焦系の動き、両手を両膝にあてるのはどっちの手と決まってますか?
A:
特に決まっていません。
例えば両手を拳で合掌したときに親指の組み方がどちらでもよいのと同じことと考えて下さい。
呼吸で下肢の氣の流れを促進させることの方が大切です。
Q:ドーシャチェックで出た結果について、どう改善するのかと聞かれた時の指導が分からない。
A:
ドーシャについて認識して頂きたいこと⇒3つの数値に大きな差がない場合は、それらのドーシャは健素と言い、健康であるとします。
一方、3つの数値の差が顕著な場合は、それらのドーシャを病素と言い不健康な状態か、病気であるとします。
まず、6つのパターンの数値を出します。
単体ドーシャ、その3つのバランスを見て下さい。大体似たような数値であれば、健康な状態とします。
どれかのドーシャの数値が大きすぎるときは、その状態が増大しているということですので病素になっているのです。
次に複合ドーシャ、その3つのバランスを見て下さい。一番大きな数値が今の状態を表していて、>との数値の差が大きい場合は要注意です。
改善方法は、それまで学んだドーシャの特徴や、ヨガ(呼吸法)の取り組み方を参考にし(テキストP190、P199)、アーユルベーダ―的生活を取り入れます。
このシートでチェックする大切なことは、病気にとなってしまう前に予できることに気づいていただき、改善方法を研究することにあります。
講師が一緒に、各々の結果について考えてあげて下さい。
ヨガはプラナヤマの在り方、アーユルベーダは食事の在り方をとても重要視しています。
食の素材選び⇒食事の時間⇒食べ方・環境⇒吸収~代謝の状態⇒排泄の状態⇒運動・休養・睡眠とのバランスを、時間生物(整理)学論で示していますので、その考え方であるP190の表を見て考察してみましょう。
Q:P50三密の所の説明はどうしたらよいか、縦横の系列の説明の仕方が分からないです。三密にヴィンヤサが関係すると思うんですが…
A:
三密にはヴィンヤサがではなくドリスディが関与します。
ドリスディとは集中するための視点です。アシュタンガヨガの言葉で、アーサナの三密の完成度を高めます。
50ページは三密行の説明です。この「行」の意味は法則を求めて意識して行う事を言います
これは沖ヨガの求道ヨガの実践に不可欠なもので、生活の一挙手一投足を意識し気づきをもちながら行う事を言います。
なのでここの三密の説明の部分は、アーサナの行いかたとポイントではなく、生活ヨガとして説明します。
まず、「統一体、調和息、統一心」とはどのような状態かを三つの○の図で説明します。
箱の二段目の調身・調心・調息をみながら説明すると良いでしょう。
次に動作を例に説明します。統一体(調身)とは、体の状態が分裂していない状態です。
皆さんは荷物を持ち上げようとするときどうしますか?どのように体を使ったら上手にできると考えますか?
統一体としての正しい答えはこうです⇒重い手荷物などは腰を痛めないように、力を充分に発揮させるために、箱を底から持ち上げるようなしっかりとした持ち方をして、膝を深めに曲げ腰を落とし、腿や殿筋の筋肉が協力しやすい姿勢で意識は丹田におき、一息!腹にぐっと留め込んでから、全身を協力させた状態で一気に持ち上げます。
沖ヨガではこれを「動作・呼吸・意識集中」の三密(身密・口密・意密)と言い、動作に呼吸や意識を合わせる大切さを生活の中で養うよう教えています。
この無理がない、つまり不必要な緊張がない、無駄がない、つまり不必要な歪みやゆるみのない体を自然体といい、その時に行われている呼吸を自然呼吸といい、その時の心を状態は自然心と言っています。
正しい姿勢では呼吸は完全に行われますし、心は最高に集中しつつリラックスする中庸な状態におかれます。
これをわかりやすく言うと、体のやわらぎ、神経のくつろぎ、心のやすらぎです。
そして八段階で表現すると、体位法、呼吸法、瞑想法であり、サンスクリット語で訳すと、アーサナ、プラナヤマ、ダラーナ・ディヤーナとなります。
マットの延長線上に生活がある。マット上で行う体位法や呼吸法や瞑想法は生活で気づくための練習なのです。従ってヨガアーサナをプラナヤマによってダラーナ・ディヤーナへと深化させて瞑想として行うことが大切です。
ヨガが単なる体操やストレッチなどのエクササイズではない理由はここに在ります。
アーサナを行っているときはアーサナが進化(深化)するのを観察し、プラナヤマ(調氣法)しながら受け入れる(タパス)、考えるのではなく感じながら意識を集中(瞑想法)させていくのです。
やがて生命の法則がよくわかり、心を手放し空け渡すこと(ダラーナ・ディヤーナ)で三昧(生命と一体に慣れた喜び)へ導かれていきます。
沖ヨガでは更に二つの段階を加えて人としての価値を深めています。(P12の図)
次にアーサナの行いかたとポイントを具体的に説明しましょう。
Q:八支則のところですが、ここでは沖ヨガの十支則の説明をすれば、パタンジャリの方は省いても良いですか?
A:
説明して下さい。パタンジャリの八支則の知識はとても大切です。
それと比較して沖ヨガの十支則の考え方を理解するのはもっと重要です。
沖先生が解釈したこと、二段階を加えた意味を次のようにしっかりとお伝え下さい。
ヤマ・ニヤマを対で考えることは意志の弱い人間が行いやすいようになっています。これは心の救済と言ってよいでしょう。
また、バクティ―を入れた意味ですが、心身の放下(ダラーナ・ディヤーナ)は、尊いもの(神、生命)への信仰心がなければできないことです。
パタンジャリの八段階はインドのバラモン教の教えですが、沖先生はさらに仏教や神道に在る教えを加えて二段階、ブッディとプラサードとしています。
あらゆるものの中に神の姿、仏心があるということ、自己冥利を手放して他を尊び、役にたつ生き方をする心(四心一行)を養うことが人生の究極目的であるという教えは、平和を願う沖先生の心そのものでしょう。
インド大使館から沖ヨガが表彰されたのも、ヨガという言葉が示す真の教えに沖ヨガが長年貢献してきたからなのです。
2021年10月12日追加
Q:130ページ12行目「捧仕してあげてよい資格のある人にだけ、捧仕するということです。」
この一行の理解が難しいです。どういう意味にとらえるのでしょうか?
A:
捧仕とは、それに一致する行いを自分が犠牲にならない状態でさせて頂く事を言います。
この時、相手の欲求に捧げさせて頂くことが正しい事なのか?の洞察が必要となります。もし相手の要求に応える事が誤ちなのであれば、その施しや行為が自他共の罪になるからです。その行為がどういう結果を生むのかということが読めないと、自己満足に終わるだけです。
例えば、子供が欲求に任せて我儘を言ったとしましょう。親はそれを諭すのが正しいのですが、つい許してしまって要求のままにしてあげる事は誤ちです。
また、努力できるのに努力をしないで他にやって貰う事ばかりを要求する人に捧仕をさせて頂くのは、その人の怠け心を助長させるという罪をつくる事になり良くありません。
<ヨガの研修でインドに行った時の体験談>
その日私達は捧仕行の学びをするため、ガンジス河を巡礼しました。
母なる聖河、ガンガマーには毎日施しを求める貧しい人達が集まります。
その日も私達の先行く道を塞ぐほどたくさんの貧しい人々が群がりました。
ガンジス河は巡礼する裕福な人の「喜捨の心」を捧げる場でもあります。
貧しい人々に施しをする人、身体が不自由な巡礼者を助けながら一緒にガンジスの沐浴をする人などがたくさんいました。
私達は喜捨の学びとして、施し物の毛布や食べ物を自分達で買って持っていくのですが、欲しがる人々にあっという間に囲まれてしまいました。
手が目の前に伸びてくるので毛布や食べ物を渡そうとしたら、あるインド人から叱られました。
その白髭のインド人は、長杖で人だかりを分けながら何やら大声で叫んでいます。
「その子は働ける、施してはならない!」「その毛布を必要としている人は他にいる!」「その子は歩く事ができない家族の為にここに来たのだ、分けてあげなさい」
相手に足るに充分なものがすでにあるのに、努力できるだけの力があるのに、欲しがってばかりなまけてばかりの人には捧仕をして頂く資格はない。
資格のない人に施す事は罪を犯す手伝いをしていることになるとそのインド人の聖者は教えているのだと、ツアーコンダクターから後に教えてもらいました。
捧仕とは本当にそれを必要としている資格を有する相手に、無私の境地でさせて頂く心を言います。
捧げさせていただく側は、的確な洞察力による慈悲の心でおこなわなければならない…ここの文章はそのような意味になります。
Q:➀92ページ「太陽黄道十二宮」
➁93ページ「マントラチャンチングはイシュワラプラニダーナにより…」
➂98ページ「神酒ソーマは.…」
このような話(書き方)を今までの養成講座では触れていなかったと思います。
個人的には聖典等々は大好きで勉強もしていますが、NPO法人としてこういったこと載せる必要はどうなのでしょうか?
質問が出たときにどう答えて行くものか?ご意見ください。
A:
新テキストはヨガの必要な知識をその章を完成させるバランスを十分に考え説明しております。
本来ヨガは宗教的な意味合いを含む精神哲学ですから、その部分を外すことはむしろ偏よりとなるでしょう。
今はヨガが世界的に認められ、国際ヨガの日も認定されています。
ヨガが単なるブームから生活文化として定着していくためにも偏らない知識を得、しっかりお伝えしていくことが大切だと考えて新テキストに掲載しました。
➀について:
太陽礼拝にある12の動きをする時、単なる体操(ポーズ)と捉えるのではなく、その流れが太陽が宇宙を巡る道が関係している事を知り宇宙法則に合わせた身体の調え方をする、と理解する事は地球上のあらゆる生命に平等にパワーを与えてくれる太陽への感謝心がより深まります。
太陽礼拝は旧テキストではアーサナの章にて紹介されていましたが新テキストではアーユルヴェーダの章での学びとなっています。
感謝の気持ちをもち、心身を健康にする努力を惜しまないという連続のポーズが、アーユルヴェーダの教えと違わないからです。
➁について:
宗教という語が一般的に使われている内容は、特殊なことを信じてその考え方以外は認めないような団体を指して使われている場合が多いのです。
宗教の「宗」は元の意味で人間が社会生活をする上で根本的な教えの意味で使うのが本来の使い方ですが、欧米から来た一神教的、排他的な信仰が日本に入った時に、religionの訳語を宗教にした為に、一般に宗教の意味が間違って使われるようになったのです。
祖先を崇拝したり、太陽や水などの生命のもとにある存在に感謝したりする行為が本来の意味の宗教なのです。
インドの語のイシュワラプラニダナを学者は自在神に祈る等の事としていますが、何のことかわからないでしょう。
まさに日本の精神的伝統には、太陽や水や樹木、大地が生命のもとであることを感じて、そこに「神」を見る心を育てることが精神修養でした。
自我の目が人間が生きていることの実態について真実の姿に気付かず、利己的・自己中心的な偏ったものの見方をしていることを戒める為に、戒に入っているのです。
イシュワラプラニダーナは神と一つになると言う訳になりますが、インドでは、聖者、尊師と言われているグルが語り継ぐ言葉(真言)を唱え、グルを通じてシヴァやビシュダ(ヌ)などの神々と繋がることを意味します。
これは多神教国インドで生まれたヨガを知る上で大切な学びです。決して宗教めいた文章ではなく、NPO法に反するものでもありません。
同ページの箱下6行目「日本ヨガ連盟では社会捧仕活動を行うための心身づくりを推奨しています」←先生達には、ここを強調してご指導お願い申し上げます。
➂について:
太陽礼拝とのバランスを考えて掲載致しました。
神酒ソーマの記述もごく一般的知識として説明頂きたいと思います。強調して頂きたいところは8行目、地球に住む生物の命は…からでしょう。
最近は満月ヨガなど、月を対象としたヨガも流行りとされています。
太陽同様に月が持つエネルギーの知識をささやかではありますが、知っておく事はヨガインストラクターとしては必要と感じています。
Q:61ページ正坐法③「両足の拇指は重ね」とありますが、重ねないのでは?
A:
旧テキストには、重ねる方法と重ねない方法のどちらも紹介されています。
重ねない場合は踵を揃えて骨盤を立てて腰の位置を高くし身構えるのですが、このやり方は比較的足首の硬い人(欧米人に多い)や、腰周りの重さが負担となる人にとっては組む事はもちろん、長く坐する事すら困難でしょう。
そこで魚のポーズ同様に比較的楽な形として、重ねる方を紹介する事としました。
加えて言うならばどちらの母趾が上下しても構いませんが、ヨガクラスの時などは、うつ伏せシャバアサナのように重ね方を変えて行うとバランスがとれるかと思います。
※五体投地法(P97)で正座から立つ時は両膝揃える一足立ちで行いますが、仏教や茶道の教え作法では片足の先を少し後ろに引いて立つ形が主流となっているようです。
このように大多数の方々が取り組みやすい形を紹介することは、集中しやすくより目的が達成できる方法として必要な事ではないかと考えます。
Q:196ページ(i)「キュアリング」とは何でしょうか?トリートメントのオイルにするために必要なことですか?
A:
キュアリングとは食品に熱処理をし、素材のピュア度や保存性を高めた状態と言う意味で使われる言葉です。
ごま油に熱処理(キュアリングcuring)をして不純物を飛ばし浄化させる事で油がしっとりとまろやかになりますので、マッサージをした時に塗り込まれる油が皮膚の代謝が高まるに伴い消化されやすくなり、よりトリートメント効果が引き出されるのです。
※太白胡麻油を使用する場合・・・10〜15本を弱火で加熱し油の中のセサモリンを抽出させます。
セサモリンは、老化や癌予防の働きをもつ。活性酸素の働きを抑え抗酸化作用をもたらすものです。
Q:77ページ弓のポーズ①「足首をつかんで」は“足首に手指をかけ”のほうが、親指を他の指にそろえて、握らないと言えるのではないでしょうか?
A:
確かに「つかむ」の言葉を改めて調べますと、親指を回して他の4本指と近づけたしっかりした握り形を意味しているものが多いです。
アーサナのやり方の説明はだいたい旧テキストに添い作成しており、旧テキストにも足首をつかみと表記があります。
写真の形を見ながら習っているものとして我々テキスト監修委員会は違和感を持ちませんでした。
新テキストも写真をご覧頂ければわかるように足首を握ってはいないので、そこはそのようにご指導ください。
2021.9.30日追加
Q:33ページ丹田呼吸の行い方の記述が分かりにくいです。この通りに行うと?
A:
丹田呼吸は腹式呼吸の応用として、丹田に氣を集める東洋に伝わる調息法です。
テキストでは氣を集めるポイントに絞って記述されています。
2021.9.26配信
Q:新教科書で表題のポーズが、今まで受講者さんにお伝えしてきたものと、今回違うのは何故ですか?
A:
旧テキストのバージョンアップとして作られた新テキストには、色々な意味合いが込められています。
まず新テキストのアーサナ選定は、取り組みやすいもの、心身の健康バランスを調え生命力を呼び起こす効果が高いものを最小限で選んでいます。
魚のポーズは見た目以上に、肘、肩、首などの関節や、腰椎の部分に対する負担が大きいアーサナです。しかし、日頃緊張している部分がリラックスし呼吸が深まる大事なポーズです。
そこで選定は必須だとし比較的優しい形を選びました。
一方、アーチや肩立ちのように難度が高いポーズは、他にはない効果が期待されるアーサナであり、かつ、簡単な形はありませんので、上級アーサナとして提示しました。